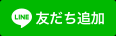医療過誤における「証拠保全」とは
医療過誤に疑念を抱いたり、実際に起こったりした場合は、事実確認の証拠として診療記録などを現状のまま入手する必要があります。
この記事では、医療過誤における証拠保全について解説します。
医療過誤における証拠保全とは
医療過誤とは、医療行為によって事故が発生した場合、医療機関側に過失があることを指します。
証拠保全とは、民事訴訟を起こす場合に、事故などを立証する証拠となるものを事前に調べて、改ざんや破棄されぬように保全する手続きを指します。
このことから医療過誤における証拠保全とは、医療行為による事故に対し、医療機関を相手に訴訟を起こす際に必要となる医療記録を保全する手続きであると言えます。
具体的には、訴訟前に医療機関へ行き、事故原因のカルテやレントゲン写真、検査結果などの医療記録をコピーやカメラ撮影などで記録します。
これは、裁判所に証拠保全の申し立てを行い、裁判所が「証拠保全決定」を認めた後に、裁判官や裁判書記官、患者側の弁護士などが病院を来院し、前述の作業を実施して証拠保全を行います。
証拠保全手続きの流れ
医療過誤における証拠保全の手続きは、以下の流れで行われます。
1. 裁判所に申し立てる証拠保全の申立書を作成する
2. 裁判所に証拠保全の申し立てを行う
3. 裁判官と面談する
4. 証拠保全期日の当日に医療機関側に証拠保全決定書を通知する
5. 裁判官、裁判書記官などが病院へ行って証拠保全を行う
6. 証拠保全の記録を書面にする
手続きの内容について詳しく解説します。
裁判所に申し立てる証拠保全の申立書を作成する
裁判所に申し立てる際には、申立書に証拠保全を申し立てる趣旨や理由、必要性を記載します。
事実経過やカルテなどの医療記録の改ざん、破棄、隠蔽などの可能性があることを具体的に記載することが重要であり、記載内容に不備がないように気をつけてください。
裁判所に証拠保全の申し立てを行う
申立書が書けたら裁判所に申し立てを行います。
その際、収入印紙と郵便切手が必要になるので注意してください。
裁判官と面談する
申立書に不備がなければ裁判官と面談を行います。
面談内容は、証拠保全期日の日程や検証物の優先順位、当日の流れなどについて打合せます。
証拠保全期日の当日に医療機関側に証拠保全決定書を通知する
証拠保全期日が事前に病院側に知れると、カルテなどの医療記録の改ざんや破棄される恐れがあるため、実行する当日の1~2時間前に医療機関へ「証拠保全決定書」を通知します。
そこで初めて医療機関側も1~2時間後に証拠保全が行われることを知るので、医療機関側に改ざんされるリスクは減ります。
裁判官、裁判書記官などが医療機関へ行って証拠保全を行う
医療機関に通知した1~2時間後に裁判官、裁判書記官、カメラマンや弁護士に依頼している場合は弁護士の方たちも医療機関へ行きます。
カメラマンは、カルテやレントゲン写真などの証拠を撮影するために同行することがあります。
裁判官は、医療機関側に対して申立書に記載のある医療記録の開示を求めた後、証拠保全を開始します。
証拠保全の記録を書面にする
医療機関でコピーや撮影した書類や写真を裁判所に持ち帰り、資料をまとめて検証調書を作成します。
医療過誤における証拠保全を行う際の注意点
証拠保全を行う際には、以下のことに注意してください。
- 自分勝手に行動すると証拠隠滅をされる恐れがある
- 証拠保全決定書に記載のない書類などは開示してくれない
- 証拠保全期日の当日だけですべての医療記録を検証できない場合がある
医療過誤が起こったり、疑ったりしたときには、感情的になって自分勝手に行動するかもしれません。
その際、あまり騒ぎを大きくすると、医療機関側も警戒して、医療記録を改ざん・破棄する可能性があるので注意してください。
また、裁判所に申し立てる際に作成する申立書に記載のないものは、証拠保全決定通知書に記載されないので、記載漏れがあるときには医療機関に開示してもらえません。
証拠保全のカルテや医療記録などが多いときや開示に時間がかかるときなどは、証拠保全期日の当日だけでは確認しきれません。
そのときは、裁判官に早い時間から始めてもらうよう交渉するか、後日改めて任意開示請求などを行う必要があります。
医療過誤に詳しい弁護士に依頼すれば、これらの注意点を熟知しているため、依頼者が望んでいる証拠保全ができる可能性があります。
また、裁判所に申し立てる場合や申立書の記載内容、医療機関への対応などについてアドバイスをもらえるので不利な立ち振る舞いを抑制できます。
まとめ
今回は、医療過誤における「証拠保全」について解説しました。
医療過誤が起こった場合や疑いがあるときは、医療機関に直接問い合わせるとカルテなどの医療記録を改ざんや破棄されて、なかったことにされる恐れがあります。
医療過誤についてお悩みの方は自分勝手に行動すると、医療機関に証拠を隠滅される可能性があるので、医療過誤や法律に詳しい弁護士に相談してアドバイスを求めることをおすすめします。
提供する基礎知識Basic Knowledge
-
不適切な麻酔による後...
麻酔は、手術や治療において痛みを和らげ、患者の安全を確保するために欠かせない要素です。しかし、時には不適切な麻酔が行われ、深刻な後遺症を引き起こすことがあります。医療過誤により損害を被った場合には、その損害に応じて、病院 […]

-
歯科麻酔によるアナフ...
医療過誤にあった場合、法律的には、示談交渉を行って示談金を得たり、訴訟を提起して損害賠償金を得ることで、解決を目指すことになります。 歯科麻酔が原因でアナフィラキシーショックが起こる確率は非常に低いですが、起こ […]

-
医療過誤と医療事故の...
病院でケガなどを処置してもらったときに適切な処置が行われず、後遺症が残ることがあります。その際、医療過誤なのか、医療事故なのか正確に判断できない方もいらっしゃると思います。この記事では、医療過誤と医療事故の違いについて分 […]

-
医療事故・医療ミスの...
医療過誤の種類はよくイメージされるような手術などの技術的なミスだけではありません。医療過誤にもいくつかの種類があり、それを把握していることによって、あの時のことは医療過誤だったのではないだろうかといった判断を行うことが可 […]

-
手術後の異物残留|慰...
手術とは、外科的危機やメスを用いて患部を切開し、治療的処置を施すことをいいます。手術を行うことは、体内への侵入を伴う点で大変危険な行為であり、医者の専門的知識・技術なくして安全に行うことができません。 もっとも […]

-
医療過誤事件に必要不...
医療裁判においては、医療に関する専門知識を持つ医師の協力が不可欠です。被告側の医療機関が医療のプロである以上、それに対抗するためには同程度のスキルを持ち合わせた人間が必要になるからです。 当記事ではこの協力医について言及 […]

よく検索されるキーワードSearch Keyword
資格者紹介Staff

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。
当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
所属団体・資格等
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
経歴
-
- 2008年
- 東洋大学法学部 卒業
-
- 2011年
- 東洋大学法科大学院 卒業
-
- 2011年
- 司法試験合格
-
- 2012年
-
弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
-
- 2013年
- 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要Office Overview
| 名称 | 初雁総合法律事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 野口 眞寿 (のぐち まさとし) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
| 連絡先 (担当:野口) |
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809 |
| 対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| LINE 公式アカウント |
当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@691yberd)
■登録方法について 
|