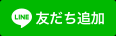帝王切開で生まれてきた子供に後遺障害|
産婦人科に対する医療訴訟は可能?
帝王切開が遅れたために子供に後遺障害が残ったり、死亡してしまった場合、父母は、産婦人科の医師や医療機関に対して医療訴訟を提起できるのでしょうか。
出産時の医療事故も医療過誤訴訟のため、ハードルは高いですが、専門の弁護士に依頼することで損害賠償請求が可能となります。
医師や医療機関に対して請求できる損害賠償の内容等について解説します。
医療訴訟とは
医療訴訟とは、正式には、医療過誤訴訟のことです。
医師が診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準に基づく注意義務を怠った場合は、過失があったものとして、医師が民法709条に基づく不法行為責任を負うことになります。
手術を行うことが多い外科はもちろんですが、産婦人科を対象とした医療過誤訴訟もあります。
また、医師だけでなく、看護師やその他の様々な医療従事者に対して損害賠償請求がなされることがあります。
医療過誤訴訟は難易度が高い?
医療過誤訴訟は難易度が高く、手掛けられる弁護士も限られているのが実情です。
医療過誤訴訟は、医師等に対して民法709条に基づく不法行為責任を追及する訴訟です。
そのため医師等の過失を原告である患者側で立証しなければなりません。
因果関係の立証については、「一点の疑義も許されない自然科学的証明」まで求められるわけではなく、「経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明すること」で足りる(最判昭和50年10月24日 民集 第29巻9号1417頁)と解されていますが、それでも立証のハードルは非常に高いです。
胎児の死亡・後遺障害につながる医療過誤
出産に立ち会う産婦人科の医師は、出産時の臨床医学の実践における医療水準に基づく分娩監視義務があります。
医師等がこの義務を怠った結果、帝王切開等の医療的措置が遅れて、胎児の死亡・後遺障害につながった場合は、医療過誤となります。
胎児の死亡・後遺障害に関する損害賠償請求の内容
胎児の死亡・後遺障害といった医療過誤が起きた場合は、患者側は医師等に対して損害賠償請求を求めることができます。
損害賠償請求の主体
損害賠償請求を行うことができるのは、胎児とその父母です。
胎児
胎児とは、母体内にいる状態の子どものことで、民法上は、出生しない限り権利能力を取得しません。
しかし、損害賠償請求に関しては、すでに生まれたものとみなすとされていることから、分娩時の医療過誤により、胎児が後遺障害等を負わされた場合は、胎児が医師等に対して損害賠償請求を行う権利を有します。
胎児の父母
胎児が医療過誤により死亡した場合はもちろんですが、重篤な後遺障害を負った場合も、胎児の父母は大きな精神的ショックを受けます。
この精神的苦痛について、医師等に補償を求めるために父母固有の慰謝料請求権を取得することがあります(民法711条)。
損害賠償請求の内容
医療過誤による胎児の死亡・後遺障害について損害賠償請求できる損害項目は、積極損害、逸失利益、慰謝料の3つです。
積極損害
胎児の父母等の家族が、胎児の死亡・後遺障害に伴い、支出を強いられた費用のことです。
主なものとしては次のようなものが挙げられます。
- 治療費
- 付添費用
- 入院雑費
- 通院交通費
- 装具、器具の購入費
- 介護費用
- 葬儀費用
逸失利益
胎児の死亡・後遺障害により、将来にわたって得られなくなった収入等のことです。
死亡逸失利益と後遺障害逸失利益があります。
慰謝料
胎児の死亡・後遺障害により被った精神的苦痛に対する補償です。
胎児の父母等の家族だけでなく、胎児自身の精神的苦痛に対する慰謝料も含みます。
具体的には次の3つです。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料(胎児自身の慰謝料、父母の慰謝料)
損害賠償請求の相手方
医療過誤による胎児の死亡・後遺障害について損害賠償請求をする相手方は主に次の2者です。
- 担当の産婦人科医、助産師、看護師等の医療従事者
- 産婦人科医等が所属する医療機関
担当の医療従事者に対しては、民法709条に基づく不法行為責任を直接追及することになります。
医療従事者の過失を立証できれば、損害賠償請求が可能になります。
産婦人科医等が所属する医療機関に対しては、民法715条に基づく使用者責任を追及する形になります。
医療従事者と医療機関の双方の責任が認められた場合は、両者の責任は共同不法行為責任となり、その損害賠償義務は連帯債務となります。
そのため、胎児や父母は、どちらに対しても、損害額の全額を請求することができます。
一般的には資力の多い医療機関に対して、全額の損害賠償を求める形になります。
まとめ
産婦人科に対する医療訴訟は、医療過誤訴訟のため、ハードルが高いですが、カルテなどの資料をそろえば、不可能ではありません。
出産時の医療過誤が原因で、生まれた子供に後遺障害が残ったり、亡くなってしまうような事があった場合は、早めに医療事故や医療過誤に詳しい弁護士にご相談ください。
提供する基礎知識Basic Knowledge
-
看護師による薬の誤投...
看護師は、入院患者のお世話や診察補助等の治療に関わる仕事を行う点で、患者の生命や健康と隣り合った仕事を行う職業といえます。 看護師が薬を入院患者等に誤投薬したことにより医療事故が生じた場合、看護師や医療機関には […]

-
医師・病院の対応や処...
医師・病院の対応、診察、診断や治療の開始が遅れたことによって症状が悪化してしまった場合、医師や病院に対して、損害賠償を請求することができるのでしょうか。歯科や整形外科での手術において神経を損傷・切断させることになったり、 […]

-
誤嚥による窒息死で過...
入院している家族が誤嚥による窒息や誤嚥性肺炎で亡くなったのは病院の過失によるものではないかと考え損害賠償請求を検討しているという方がいらっしゃいます。しかし、誤嚥による窒息死のすべての事例で医療機関や介護事業者側の過失が […]

-
医療過誤事件に必要不...
医療裁判においては、医療に関する専門知識を持つ医師の協力が不可欠です。被告側の医療機関が医療のプロである以上、それに対抗するためには同程度のスキルを持ち合わせた人間が必要になるからです。 当記事ではこの協力医について言及 […]

-
意見書(私的鑑定意見...
医療過誤事件では、当時の医療水準に照らし合わせて、それを下回る医療が施されていたのかどうかが重要な争点となります。そのため医療文献の提示とともに重要なのが、この私的鑑定意見書です。これは医師の手によって作成され、原告、被 […]

-
レーシック手術の後遺...
医療過誤にあった場合、法律的には、示談交渉を行って示談金を得たり、訴訟を提起して損害賠償金を得ることで、解決を目指すことになります。 レーシック手術では、術後に合併症が発症する恐れがあり、医師としては合併症につ […]

よく検索されるキーワードSearch Keyword
資格者紹介Staff

法律を知らないばかりに悩んでいる人々の力になりたい。
当事務所は医療過誤のご相談に豊富な経験がございます。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
所属団体・資格等
- 第一東京弁護士会 住宅紛争処理審査会運営委員会 委員会
- 医療問題弁護団
- 公益社団法人 東京青年会議所
- 文京区基本構想推進区民協議会 委員
- 公益財団法人 文京アカデミー 評議員
- 文京区倫理法人会
経歴
-
- 2008年
- 東洋大学法学部 卒業
-
- 2011年
- 東洋大学法科大学院 卒業
-
- 2011年
- 司法試験合格
-
- 2012年
-
弁護士登録 第一東京弁護士会(登録番号46872)
神保町法律事務所 入所
文京区 行財政改革区民協議会 委員 就任
東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー 就任
公益社団法人東京青年会議所 入会
-
- 2013年
- 初雁総合法律事務所 設立
公益財団法人文京アカデミー 評議員 就任
事務所概要Office Overview
| 名称 | 初雁総合法律事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 野口 眞寿 (のぐち まさとし) |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-4-4 水道橋ビル4F |
| 連絡先 (担当:野口) |
TEL:050-3184-3790/FAX:050-3730-7809 |
| 対応時間 | 10:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土日祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| LINE 公式アカウント |
当事務所ではLINEでの相談対応が可能です。(LINE ID:@691yberd)
■登録方法について 
|